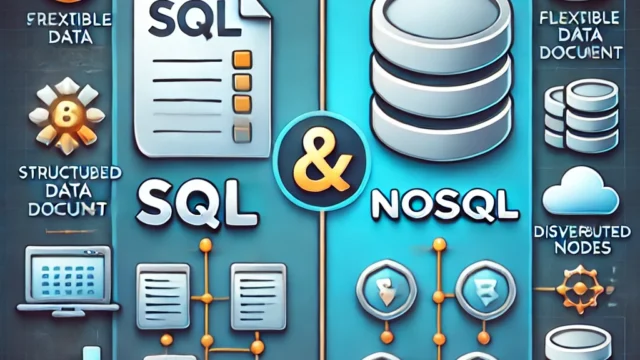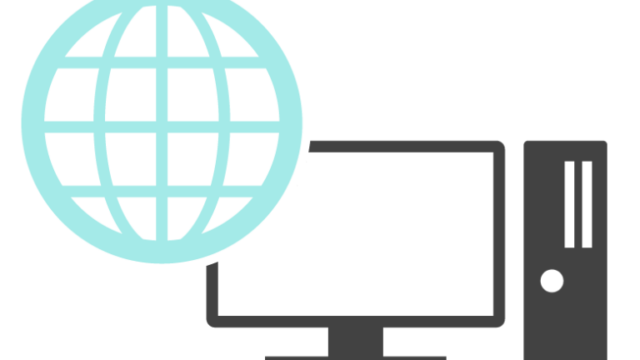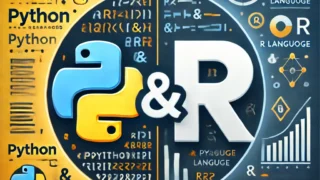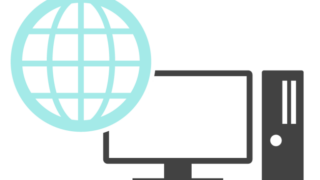Web開発やインフラの分野でよく聞く「サーバー」と「サーバーレス」。どちらもアプリケーションを動かすために使われますが、仕組みや運用方法、コスト構造などに大きな違いがあります。この記事ではサーバーとサーバーレスの違いについて、初心者にもわかりやすく解説し、それぞれのメリット・デメリット、適した用途を比較していきます。
サーバーとは?
サーバーとは、アプリケーションやWebサービス、データベースなどを常時稼働させるためのコンピュータ(物理 or 仮想)です。オンプレミスやクラウド上に構築され、開発者や運用者が直接管理・保守を行います。
サーバーの主な特徴
- 常時稼働し続けるインスタンス
- OSやミドルウェアの管理が必要
- 柔軟な構成が可能(メモリ、CPUなどを指定)
- トラフィックに応じたスケーリングには手動対応が必要なことも
代表的なサービス例には、EC2(AWS)、Compute Engine(GCP)などがあります。
サーバーレスとは?
サーバーレス(Serverless)とは、開発者がインフラを意識せずにコードの実行に集中できるアーキテクチャです。実際には裏でサーバーは存在しますが、それをユーザーが管理しなくてもよいのが大きな違いです。
サーバーレスの主な特徴
- イベント駆動型(リクエスト時のみ稼働)
- サーバーの構成や稼働時間を意識しなくてよい
- 自動スケーリング機能が標準搭載
- コストは実行時間ベースで課金される
代表的なサービス例には、AWS Lambda、Google Cloud Functions、Azure Functionsなどがあります。
サーバーとサーバーレスの違いを一覧で比較
| 項目 | サーバー | サーバーレス |
|---|---|---|
| 管理の必要性 | OSやパッチなど運用保守が必要 | ベンダー側がインフラ管理 |
| 起動方法 | 常時起動 | リクエストに応じて起動 |
| コスト構造 | 時間ベース(常時稼働で課金) | 実行回数や実行時間ベース |
| スケーラビリティ | 手動スケーリングが多い | 自動スケーリング対応 |
| 自由度 | 環境を自由に構成可能 | 制限があるが簡単に始められる |
| 起動速度 | 高速(常時起動) | 初回起動はやや遅い(コールドスタート) |
サーバーが向いているケース
以下のような場面では、従来型のサーバーが適しています。
- 高トラフィックなWebサービスを常時提供する場合
- 独自ミドルウェアやカスタム設定が必要な場合
- 継続的なバックグラウンドプロセスを動かしたい場合
- システムの詳細なコントロールが必要な企業システム
サーバーレスが向いているケース
サーバーレスは以下のようなシナリオで真価を発揮します。
- 突発的なアクセスに自動で対応したい
- 小規模なAPI、バッチ処理、イベント駆動型システム
- 初期コストを抑えてすぐにリリースしたいスタートアップ
- インフラ管理を最小限にして開発効率を上げたい
注意点とデメリットも把握しよう
サーバーのデメリット
- スケーリングや障害対応が自前で必要
- 未使用時でもコストがかかる
- メンテナンス作業の工数がかかる
サーバーレスのデメリット
- コールドスタートによる遅延
- 実行時間・リソースに制限がある
- ベンダーロックインのリスク
- 常駐サービスや長時間処理には不向き
まとめ:使い分けが重要!
サーバーとサーバーレス、それぞれに強みと弱みがあり、用途に応じた使い分けが重要です。大規模システムや高いカスタマイズ性が求められる場面では従来型のサーバーが有効。一方、イベント駆動型やスモールスタートにはサーバーレスが最適です。
- インフラを自由に構築・制御したい → サーバー
- 管理負荷を減らし、柔軟なスケーリングを重視 → サーバーレス
また、実際の現場では両者を組み合わせたハイブリッド構成も一般的です。技術選定の際は、自社の要件やリソース、スキルセットに応じて最適な方式を選びましょう。